前回の記事では、500円のクラウドワークス案件が実務級の4,000字ライティングになった体験について書きました(詳細はこちら → https://kenjinext47ai.com/crowdworks-experience-500yen/)。この成功体験は、AI学習と生成AI活用の可能性を感じさせてくれるものでした。
それを受けて、今回からは教材に沿って Dify学習の本格的なフェーズ に入ります。
とはいえ、最初から順調には進まず…。「チャットフロー」で迷子になり、気づけば1日以上を浪費してしまったのです。
これから、その失敗と気づき、立て直しのプロセスを赤裸々に綴ります。
Dify学習の序盤でつまずいた大失敗
教材との違いに戸惑った瞬間
Dify学習を始めた初日、いきなり大きな壁にぶつかりました。教材では「チャットボットを作ろう」と説明されていたのに、なぜか自分は「チャットフロー」から作業を始めてしまったのです。画面の見た目が教材と違っていたため、「仕様が変わったのかもしれない」と早合点してしまい、ChatGPTで最新情報を調べながら独自に進めることにしました。
ところが、ブロックやノードを組み立てても思うように動かず、試行錯誤を重ねるうちに時間だけが過ぎていきます。何度修正しても完成形が見えず、「またかよ…」とため息をつきながら作業を続けました。結果として、丸一日以上を無駄にしてしまう痛恨のスタートとなりました。
1日以上無駄にした苦い経験
一旦すべてを削除して最初からやり直そうとしたとき、自分が「チャットボット」ではなく「チャットフロー」で作業していたことにようやく気づきました。「何やってんだ俺は…」と苦笑しつつも、教材通りに進めることが正しいと理解できた瞬間でした。Dify学習の入り口でつまずいたものの、この気づきがなければ正しい進め方に戻れなかったでしょう。
チャットフローとチャットボットを勘違いした理由
教材では「チャットボット」で学習を始める前提でしたが、DifyのUIは直感的に「フローから作る」ほうが自然に見えます。そのため、自分も無意識にフローを選択してしまったのです。ここで学んだのは、画面に惑わされず教材をしっかり確認すること、そして「最新仕様に違いない」と決めつけないことでした。
気づいた瞬間と立て直しのプロセス
誤りに気づいた後は、教材の指示通りに「チャットボット」を構築。正しい入口に戻っただけで、すべてがスムーズに進み始めました。Dify学習においては「入口の選択」が何よりも大切で、最初の一歩を間違えると時間も労力も大きく浪費してしまうことを実感しました。
プロンプト構築ボットを作ろうと決めた経緯
教材の例では、自分には必要性のないチャットボットを作る流れでした。そこで「どうせ作るなら自分に役立つものを」と考え、プロンプト構築ボットをテーマに選びました。これまでの学習で得たプロンプトの基礎から完成形までをナレッジベースに落とし込み、Dify上で検証。ChatGPTでの出力と比較しながら固定プロンプトを設定し、分析と調整を繰り返しました。
ナレッジベースの作成と反映チェック
Dify学習の強みは、ナレッジベースを組み込んで独自のチャットボットを作れることです。自分のプロンプト理論を投入した結果、しっかりと反映されているのを確認できました。ここで初めて「学んできたことが仕組みに転換されている」と実感でき、生成AIを使った学習が次のステージに進んだ手応えを得ました。
固定プロンプトの設定と検証
続いて固定プロンプトを入力し、出力された結果を分析。期待通りに動作する部分と、まだ調整が必要な部分を洗い出しました。Dify学習では「一度作って終わり」ではなく、検証と改善のサイクルを回すことが重要だと理解しました。
API連携と課金による実験環境の完成
実際に使うためには外部サービスとの連携が必須です。OpenAI、Cohere、Anthropic、Notion、markitdown、MinerUといったプラグインをAPIキーで接続。さらに動作確認のために500円だけ課金し、ようやく実験環境を完成させました。小さな投資でしたが、自分のDify学習を一歩前進させる大きなきっかけとなりました。
Dify学習序盤から学んだことと今後の展望
今回の失敗を通じて得られた教訓は明確です。正しい入口を選び、目的を持って学習を進めること。そして教材を鵜呑みにするのではなく、自分の目的に合わせて応用していく姿勢が不可欠です。
Dify学習は、AIや生成AIの活用を単なる実験から「実務に使える仕組み」へと昇華させる力を持っています。序盤の失敗すらも学習の糧にしながら、今後はさらに高度なフロー設計や自動化に挑戦していくつもりです。
よくある質問
Q1. 入口はどこから作る?
A. 最初は「チャットボット」から。フロー図は後で大丈夫。
Q2. ナレッジは何個入れればいい?
A. 初日は1ファイルで十分。少ないほど動作確認しやすい。
Q3. プロンプトはどのくらい書けばいい?
A. 1行でOK。「知識の範囲で答えて。最後に根拠を1行。」これで十分動く。
🔗関連・前後記事
🧩前:500円面談が4,000字実務に化けた日|一次情報で2時間完走
🧩次:月少コストで走る:私が使っているAIツールとWeb/アプリの使い分け
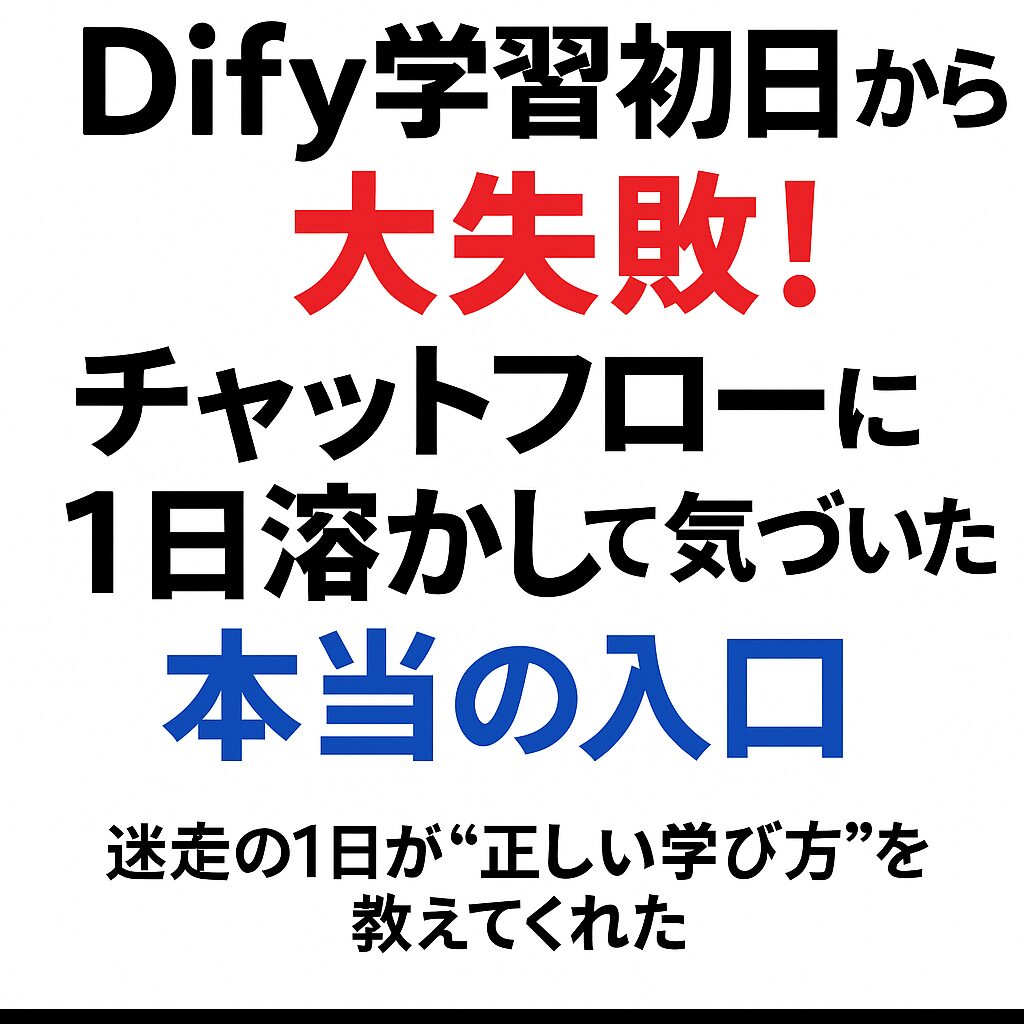
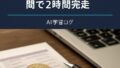

コメント