前回の記事では、Difyを使って月少コストで回すAI環境を紹介した。
ドメインとサーバーで月1,200円台、ChatGPT PlusとAPI少額で十分に運用できる。
今回からは、その環境をどう“仕組み化”したか――つまり、AIで時間を増やすための構造づくりについて書いていく。
実際に取り組んだのは、トークン超過を防ぎつつ精度を維持する設計「compact-HQ」。
この仕組みが動き出してから、AI学習がようやく“日常の中に溶け込む”感覚を得た。
Dify学習の転機:限界値を見つけた瞬間
Difyを本格的に使い始めた頃、最も苦しんだのはトークンオーバーだった。
構成を増やすほど出力が不安定になり、ナレッジが増えるたびに精度が落ちる。
削っては足し、整えては崩れる。
そんな試行錯誤の中で見えてきたのが、“量ではなく上限”の考え方だった。
Difyの無料枠はナレッジ50件・容量50MB。
そのうち私は48件で止めている。
49件目を追加すると、検索スコアが下がる。
つまり「48」という数字が、安定動作の限界点だった。
この体感値を掴んだ瞬間、調整の方向が明確になった。
compact-HQ:1700文字に詰めた最適構造
compact-HQとは、高品質なプロンプトを1,700文字前後に圧縮した設計のこと。
目的は単純で、短くしても精度を落とさない。
従来のプロンプトは長いほど安心感があるが、AIは全体を把握しきれない。
そのためI/O契約(入力・出力・成功条件)を冒頭で定義し、不要な修飾や曖昧表現を削除。
結果、短くても再現率の高い“核”だけが残った。
CohereのRerankをONにし、Top-K=4・閾値0.2に固定。
これにより、トークン超過がほぼゼロ。
再現性の高い出力が安定した。
ノイズを減らすほど、品質が上がる。
その実感がcompact-HQの核心にある。
AIが生むのは「時間」ではなく「余白」
compact-HQを導入してから、AIに任せる範囲を決められるようになった。
結果、出力を待つ時間が“思考の余白”に変わった。
AIが仕事を奪うのではなく、人間が**「考える」ためのスペースを取り戻す**。
AIで時間を増やすとは、タスクを減らすことではなく、
判断のための時間を再構築することなのだと気づいた。
知識を増やすより「構造を整える」
多くの人は、AIを上手く使うためにナレッジを増やそうとする。
だがDifyを使い込むほど、量より一貫性が重要だと分かる。
ナレッジが48件になってから、ようやく“削る勇気”が持てた。
構造を整えると、AIの反応は驚くほど明快になる。
AIは知識の多さではなく、構造の明晰さに従う。
この理解が、すべての基盤になった。
compact-HQは「安定運用の入口」
compact-HQはゴールではなく、運用の安定点だ。
これでようやく、週単位のメンテナンスに移行できる。
ナレッジを整理しながら、毎週少しずつ更新するだけで成果が積み上がる。
Dify学習はまだ続く。
だが、もう“試行錯誤のループ”には戻らない。
仕組みは整った。
これからは、その仕組みで時間を取り戻すだけだ。
🔗 参考リンク
Dify公式サイト:https://dify.ai Dify
Difyクラウド(ログイン):https://cloud.dify.ai/ cloud.dify.ai
Difyドキュメント:https://docs.dify.ai/ Dify Docs
価格・プラン:https://dify.ai/pricing Dify
公式GitHub(本体):https://github.com/langgenius/dify GitHub
公式ドキュメントGitHub:https://github.com/langgenius/dify-docs GitHub
会社や学校のフィルタ/拡張機能でブロックされることがあります。開けない場合は cloud.dify.ai(ログイン直通)か、ネットワーク変更(モバイル回線・別DNS)をお試しください。 cloud.dify.ai+1
🔗関連・前後記事
🧩前:月少コストで走る:私が使っているAIツールとWeb/アプリの使い分け
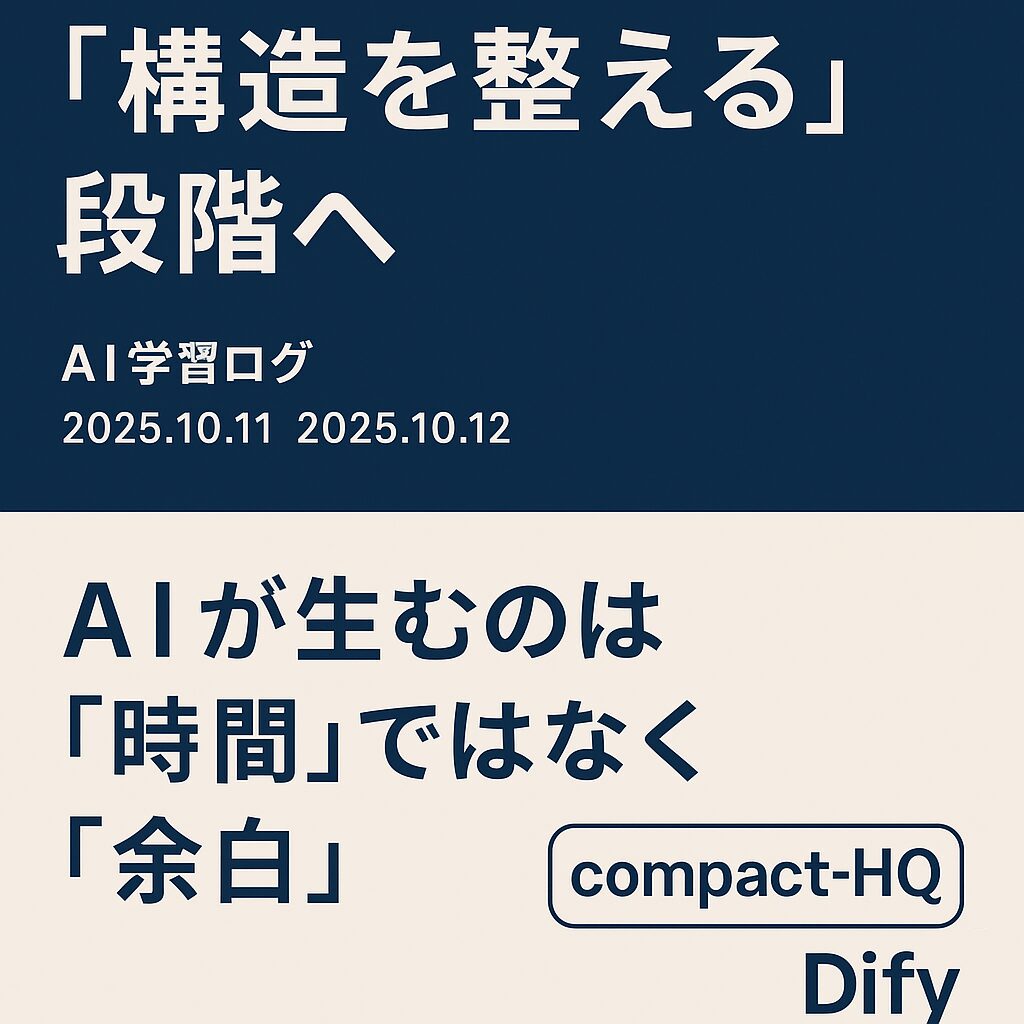


コメント