現場の実感が背中を押した
私はカジノディーラーを経て建設業に携わってきました。人手不足や安全、段取りの属人化に直面するたび、「このままでは現場が持たない」と感じていました。AI学習を始めた決め手は、その違和感です。47歳・未経験でも、まずは自分の手で触れて確かめる。完璧より行動を優先し、短い時間で“できた/できない”を切り分けるところから始めました。最初の一歩は大げさな準備ではなく、メモ帳と簡単なプロンプトだけでした。
このシリーズの読み方
第1章:AIを学び始めたきっかけと最初の気づき
第2章:実務級記事を書けたプロセス
第3章:Difyの失敗
最新章:ツールとコストの公開
順に読まなくても理解できますが、連続して読むと学習の流れがつかめます。
最初の1か月で分かったこと(結論)
AIは現場の重たい工程をいきなり置き換えるより、書類や文章、報告のような“伝える作業”で先に効きます。文章の骨子出し、要点の整理、言い回しの統一など、バックオフィス的な領域から成果が見えました。
もう一つの結論は、理解より再現です。「わかるまでやらない」ではなく「動く最小手順を決めて、同じ結果をもう一度出す」。この回転が、学習を前に進めました。
小さく使うほうが速く進む
最初から万能を狙うと、設定や情報収集で疲れてしまいます。私は「見出し案3つを出す」「メールの骨子を100字で作る」といった小さな目的を一つだけ置き、達成したらメモ化しました。
使い道を増やすのは、そのメモを並べ替えるだけ。学習時間は短くても、効果は積み上がりました。
書類と文章から成果が出た
建設現場での報告や依頼文、見積の前置き、注意喚起の文章など、言葉の整理が早く正確にできるほど、仕事は前に進みます。AIは“言い切る勇気”を与えてくれました。
文末の曖昧さを減らし、主語と目的語を整えるだけで、意思疎通の齟齬が減りました。これは現場でもすぐ利益になります。
学びの設計:触って試し、すぐ記録
私のやり方は単純です。
① 最小プロンプトで動かす
② 得られた結果を10行で記録
③ 翌日に同じ手順で再現
上手くいけば項目を増やし、失敗したら原因を一行で書く。記録は“評価”ではなく“次の工程表”です。
これなら年齢や経験に関係なく、同じ速度で積み上がります。
失敗の扱い方:やらかしは素材
プロンプトが空回りしたり、意図しない文が返ってきたり、失敗は数え切れません。
ただ、失敗は次の見出しに化けます。「なぜ伝わらないか」を言葉にすると、次のプロンプトが締まります。
私の場合、冗長な条件を削ぎ落とし、優先順位を明確にすると、返答の質が一段上がりました。
これからの方針
当面は“学びと発信”の往復です。一次情報(自分の手で試した事実)を中心に、再現できる手順を記事に落とし込みます。
次の段階では、Difyなどの仕組み化ツールを使い、同じ品質の出力を安定して得ることを目指します。
大切なのは「誰がやっても同じ結果に近づく」ことです。
読者の方へ
AIは遠い専門技術ではありません。私のように47歳・未経験からでも、1か月で“使える実感”まで届きました。
必要なのは、大きな目標ではなく、小さく動く手順です。
この記事が、その最初の一歩を踏み出す合図になればうれしいです。
次回は、具体的な手順とプロンプトの組み方を公開します。
🧩次:私がAI学習に踏み切った2つの理由|“遠い技術”が“使える道具”に変わった日
🧩ホーム:47歳からの本気AIリスキリング|最短で“使える”へ
🧩chatGPTを使いこなす:YouTubeショート実証:視聴維持と「Engaged Views」優先の挙動(2025/11 検証ログ)
🧩 関連ページ:AI学習ログまとめはこちら
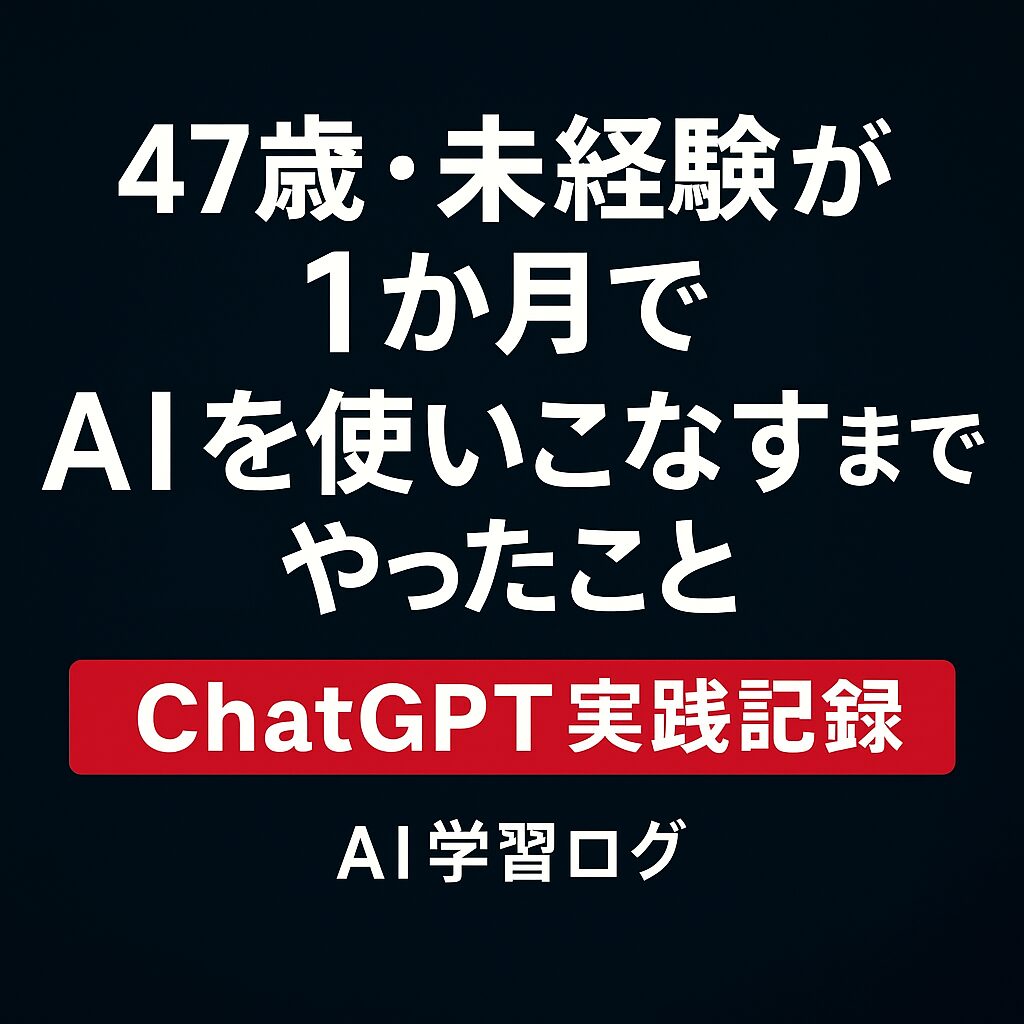

コメント