AI学習は、思っているよりずっと簡単だ。
私は特別な理論も難しい設定も使わない。
教材を使いながら、AIに判断を委ねて、淡々と進める。
それでも結果は出るし、学びは積み上がる。
AI学習の始まりは教材から
教材をコピーしてAIに投げるだけ
私の学習はいつも、教材から始まる。動画とテキストがあって、内容を理解するより先に全部コピペしてChatGPTに投げる。
「これから以下の講義を受講します」と入力すれば、AIが準備を整える。
私は内容を完全に理解していなくても、AIに説明を返させて進める。
この“ざっくりスタート”が意外とちょうどいい。
理解より実行を優先
私はアウトプット量を重視している。
理解してから動くより、動きながら理解する方が早い。
AIの回答を読んで、自分の行動に落とし込むだけ。
学んだかどうかを判断するのはAIの役割で、私ではない。
AIに理解を判断させるという発想
自分で判断しない仕組み
私は「理解できたか」を自分で判断しない。
代わりにAIに聞く。「次に進んでいい?」と。
AIが「OK」と言えば、そのまま次へ進む。
これだけで迷いが消える。学習が止まらない。
AIに委ねることで続く
この“継続の仕組み化”こそが、AI学習ログ全体に通じる共通テーマだ。
多くの人は、途中で「理解できた気がしない」と止まる。
でもAIに判断を任せると、停滞がなくなる。
私はただ質問を投げ、答えを受け取り、進むだけ。
それが継続の仕組みになっている。
教材ボット×ChatGPTの合わせ技
両方の出力を突き合わせる
教材にもAIチャットボットが埋め込まれていて、おそらくDifyで作られている。
私は教材ボットとChatGPTの両方に同じ質問を投げる。
出力を突き合わせると、微妙な差が見えてくる。
どちらが正しいかではなく、差を読むのが一番早い。
差分を学びに変える
片方が完全否定することはない。
どちらも「完璧です。でも…」から始まる。
AI同士が穏やかに補正し合うことで、誤差が浮かび上がる。
この構造が、私にとって最高の教材になっている。
結果的にハルシネーションを防いでいた
整合性が生む信頼性
AIは時に間違う。だが、二つのAIを並行で使うと、
片方の誤りをもう片方が整合化する。
これが自然に“誤情報の除去”になっている。
結果的に、私はハルシネーションをほぼ防げていた。
検証の手間を減らす
AI同士を組み合わせることで、検証工程が半分になる。
私は出力の差を見るだけで、正確さを判断できる。
複数のAIを動かすのは難しそうに聞こえるが、
実際は「コピペして投げる」だけだ。
たった一言でAIは変わる(でも教えないw)
魔法の一言の存在
たった一言をプロンプトに書くだけで、AIの精度は劇的に変わる。
その言葉はここでは言わないけれど、確かに存在する。
複雑な設定も長いプロンプトも要らない。
学び方を少し工夫するだけで、AIは別物になる。
学びの本質はシンプル
AI学習は“がんばる”ものではない。
教材を投げ、AIに判断させ、出力を突き合わせるだけ。
それでも成果は出るし、理解も深まる。
続けられる理由は、簡単にしているからだ。
🔗関連・前後記事
🧩次:ノートPCでもAI制作はできる──私の実機環境と安定化メモ


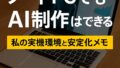
コメント