アウトプット過多とopen_url停止の混乱期
量が一気に増え、時間が常に不足した
40日を過ぎた頃、アウトプットの量が急増した。
学ぶ時間より、形にする時間の方が長くなり、常に時間が足りなかった。
記事を書き、設定を試し、結果を記録する──その繰り返し。
机に向かう時間は増えているのに、終わりが見えなかった。
10/15に発生したopen_url停止
2025年10月15日頃、ChatGPTの open_url 機能が突然使えなくなった。
外部サイトを読み込み、要約してもらう作業がすべて止まった。
混乱したが、今振り返ればここが転機だった。
自分の手で調べ、FirecrawlやDifyを組み合わせて再構築。
ツールが止まっても、思考が動き出した最初の瞬間だった。
ツールが止まっても学びは止まらない
AIが止まっても、学びは止まらなかった。
むしろ「AIに任せる」から「AIを理解して動かす」へ考え方が切り替わった。
混乱の中で、少しずつ“構造”という感覚を掴み始めていた。
保存と再現で成長が加速した理由
保存と再現の意識が生んだ変化
この頃から、「行動したことをどう再現するか」を意識するようになった。
ただ動くだけでなく、手順を残す。
それだけで翌日の自分が、もう一度同じ結果を出せる。
失敗しても、やり直しがきく。
再現できるようになってから、成長の速度が一気に上がった。
Notionにコピペでも十分効果があった
完璧な仕組みではなく、Notionにメモをコピペするだけでも効果はあった。
手順や気づきを短く残すことで、再現率が上がる。
その習慣が定着してから、思考と行動の「蓄積」が見えるようになった。
AIとの対話が安定して作業が楽になった
AIとの対話も安定し、指示が短くても意図が伝わるようになった。
この頃のAIは、まるで同じ方向を見て動く“相棒”のようだった。
以前のように細かく修正する必要が減り、作業がどんどん楽になっていった。
この“再現の仕組み化”こそ、AI学習ログ全体に通底する実践テーマである。
マネタイズへの焦りと方向転換
形にしないといけないという焦り
気づけばAI学習を始めて1か月半。
「そろそろ何か形にしないと」という焦りが出てきた。
クラウドワークスを覗いてみたが、安価な案件や勧誘目的の募集ばかり。
現実を痛感した。
応募をやめ、整える方向へ
中には連絡を返さないクライアントもいた。
時間ばかり取られる現状に、モチベーションが下がった。
その日、決めた。
「もう無理に応募はしない。自分のポートフォリオを整えて、
必要とされる側になろう」と。
ブログに残した記事、AIで作った映像、PC安定化の記録。
それら全部が、自分の“実務履歴”になる。
焦りの中で生まれたこの決断が、次のステップを準備する時間になった。
明日できる一歩
完璧より、仕組みを積み上げる
- 完璧じゃなくても、記録を残す
- 保存できる形で、行動を可視化する
- 無理に探さず、準備しながら待つ
- 焦りは、次の方向を見つけるためのサイン
マネタイズはまだ形になっていない。
でも、焦りながらも“整える”ことを選んだのは間違いじゃなかった。
動ける土台を作ることが、最初の成果だった。
あの頃の私は、まだ道半ばだったけれど──
少なくとも、次の一歩を踏み出すための位置には立てていた。
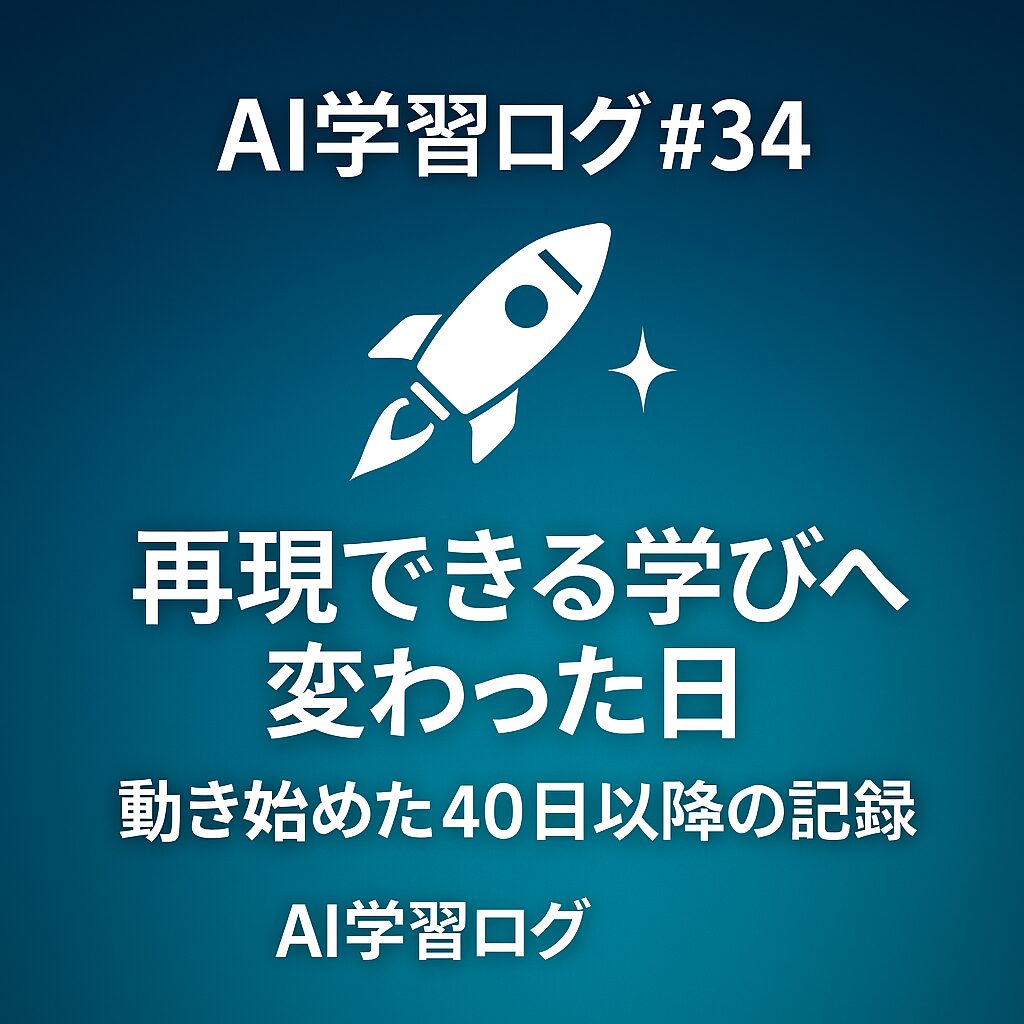

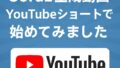
コメント