学習10日目の訪問とふれあい予約
2025年9月10日。AI学習を始めて10日目。
私は事前にLINEで受け取った1枚の写真に強く惹かれ、板橋区の**「のびも15」さん**にふれあい予約を入れて足を運びました。
予約は購入のためではなく、まず触れ合いの時間をもらう仕組み。
店内で小さな女の子と対面したとき、写真の印象そのままに、片耳だけがぴくりと動く仕草が目に留まりました。
準備として飼育情報を調べ、フクロモモンガの寿命が10年近いと知ったことも背中を押しました。
寿命の誤解を正して踏み切れた理由
私は長らく「小動物は寿命が短い」と思い込んでいました。
しかし調べ直すと、その認識は誤りでした。
さらに、現場仕事の負担とストレス、飲酒の増加、半年に一度の健康診断での糖尿病判明――
この積み重ねが**「働き方を見直すべき」**という確信につながりました。
現場を離れたタイミング、たまたまの高額勝ち、そして誤解の修正。
すべてがそろい、迎える決断に至りました。
癒しが必要だと、はっきり自覚していたのです。
のびも15で得た“正しい知識”
日本と米国の差、誤情報の多さ
のびも15さんはブリーダー兼販売、さらに研究も行う専門店でした。
フクロモモンガが日本でペットとして扱われ始めてまだ約10年。
一方、米国では約20年の蓄積があり、情報の深さに差があります。
そのため日本では誤情報が広がりやすく、
正解は一次情報に近い現場にあることを知りました。
夜行性との付き合い方と臭腺の真実
広く流布する「夜行性だから夜に遊ぶと良い」は、慣れるまでは逆効果になり得ます。
夜は日中の約3倍のスピードで活動し、視力も夜に特化しているため、明るい環境では見えづらい。
まずは昼の眠たい時間に触れ合う方が懐きやすいと教わりました。
また「オスは臭い、メスは臭くない」という断定も誤り。
メスにも育児嚢に臭腺があり、においは個体差が大きいとのこと。
私はこの誤情報のせいで最初からメスと決めつけていましたが、実情を知って認識を改めました。
群れの習性と多頭飼いの選択
フクロモモンガは本来群れで行動する動物です。
当初は1匹の予定でしたが、専門家から多頭飼いの安定性をうかがい、二匹を迎える判断をしました。
初めから「生活設計」を意識し、環境と時間を用意する前提でスタートできたのは大きな収穫でした。
名づけとこれからの暮らしの設計
片耳サインから「ミミ」、響きを分けた「エル」
気になっていた写真の子は、片耳だけを動かす愛らしい癖がありました。
第一印象を大切に「ミミ」と命名。
名前を呼び続けることで自分の名を判断できると聞き、混同を避けるため二匹目は
**響きが全く違う「エル」**に。
二匹が互いに混乱しない呼び分けは、信頼づくりの最初の一歩です。
仕事と健康の限界、癒しが必要だった理由
アスベスト除去の現場は、体力と神経をすり減らします。
ストレスから飲酒が増え、健康診断では糖尿病が判明。
いつまでも続けられない働き方を前に、
私には癒しと、日々を整える軸が必要でした。
迎え入れる判断は感傷ではなく、生活再設計のための選択。
二匹と暮らす準備をすると、こちらの生活も自然と整っていきます。
明日からできる一歩(触れ合いと観察の手順)
- 昼の眠たい時間に1〜3時間、手を巣袋に添えるだけの触れ合いから始める。
- 反応を観察 → (耳・目線・しっぽ・震え)刺激を増やしすぎない。
- 名前を個別に呼び分け、反応が良い音の高さを探す。
- においは個体差と理解し、環境清掃と換気を習慣化。
- 時間帯と触れ合う長さの小さな実験を行い、二匹の安心が増える条件を見つける。
🔗関連記事
📸 ミミ&エルの日常はこちら → Instagram(@mimi_elle_momonga)

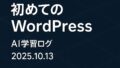
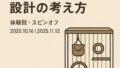
コメント