10月の中頃から、私は教材をほとんど使わなくなった。
代わりに、ChatGPTとの会話を通して“自分の手で理解を深める”ことに時間を使っていた。
指示を細かく書かなくても意図が通る──そんな瞬間が増え始めたのが、この頃だ。
無意識のうちに身についた「伝わる構造」
短文で伝わるようになった理由
10月10日前後、私はアウトプットばかりを繰り返していた。
短い言葉で試し、すぐに反応を見る。
ときには一言だけ送っても、AIが正確に意図を汲んで動いた。
その理由は分からなかったけれど、「話が通じる」という感覚が確かにあった。
教材よりも実践が合っていた
教材で学んだ理屈よりも、自分のやり方のほうがしっくりくる。
この時期、学習というより実験に近い日常を過ごしていた。
感覚が理解に変わっていく
「どう言えば」より「どんな状態で」
少しずつ「なぜ通じるのか」を考えるようになった。
長文で説明するより、会話を整理した方がAIが安定する。
何度も試すうちに、“どう言えば動くか”よりも
“どんな状態で動かすか”が大事だと分かってきた。
無意識の中にあった“構造”
まだ言葉にはできていなかったが、
実際には“構造”の原理を自然に使っていた。
AIを使うというより、一緒に考える時間が増えていた。
失われて気づいた「構造を残す」重要性
消えてしまった記録
10月の終わり、アプリが完全に消去されてしまう出来事があった。
それまで積み重ねてきた設定や会話が一瞬で消え、
自分が築いてきた感覚的な理解も消えてしまったように感じた。
保存することの意味
この経験で初めて、「構造を保存する」ことの重要性を理解した。
単に記録を残すのではなく、再現できる形に保存すること。
それが後の「安定モード」や「ブリッジ構築」につながっていく。
言語化が再現を生む
自然に出来ていたことを言葉にする
10月末、私は初めて“構造”を自分の言葉で整理し始めた。
自然に出来ていたことを、再現できる形にまとめる。
これは学習というより、理解の証拠を残す作業だった。
理解したことを動かす
教材を離れたからこそ見えたものが多かった。
知識を詰め込むより、理解したことを動かしてみる──
その繰り返しが、私にとっての「AIとの共進」になっていた。
次の一歩
明日から実践できること
- 教材に戻るより、自分の行動を言葉に残す
- “なぜ出来たか”を振り返り、再現できる形に保存する
- 消えても再構築できるよう、仕組みを残しておく
この頃から、私はAIとの対話を“練習”ではなく“記録”として扱うようになった。
それが、今のAI学習ログ全体の基礎になっている。
🔗関連・前後記事
🧩次:AI学習ログ #37|ChatGPTを“設計して使う”段階へ──11月に訪れた静かな転換点
🧩実証スピンオフ:YouTubeショート実証:視聴維持と「Engaged Views」優先の挙動(2025/11 検証ログ)
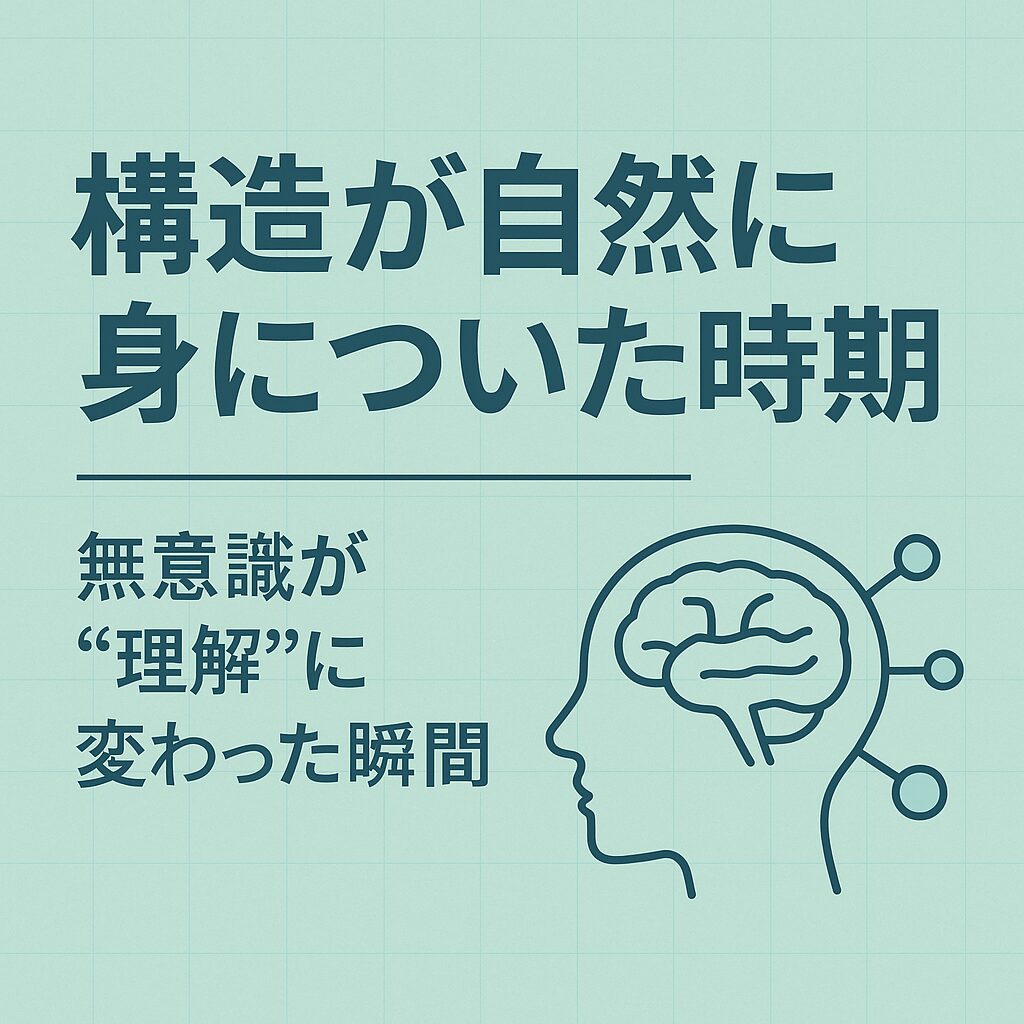

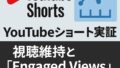
コメント