学び始めた当初、AIにすべてを任せていた。
プロンプトで指示を出し、教材を進め、記事までChatGPTに書かせていた。学習も執筆も自動で進むように感じ、私はただ「見ているだけ」の存在だった。だが、作業を繰り返すうちに、思考の輪郭が少しずつ自分の中に戻ってくるのを感じ始めた。
AI任せの学習が始まりだった
教材も記事もAI主導だった
学習を始めた当初、私はAIにすべてを委ねていた。
教材の要点をまとめるプロンプトを出し、出力を確認するだけ。記事の構成も書き出しもChatGPT任せで、私は学んでいるというより、AIの動作を眺めていた。WordPressの立ち上げも同様で、プラグイン設定やセキュリティ調整、SEO最適化まで、AIの指示に従って実行するだけだった。
「理解しないまま出来る」経験
当時は「何となく動いている」感覚が強かった。
自分では仕組みを理解していないのに、サイトが整っていく。AIが出す手順通りに作業すれば形になるため、短期間で記事が増え、SEO対策も進んだ。だがその一方で、「自分は何を学んでいるのか」という疑問が少しずつ積もっていった。
吸収の感覚とスピードの変化
無意識のうちに理解が進んでいた
数日が過ぎる頃、AIに聞かずに設定を直せる自分に気づいた。
毎回同じ質問を繰り返すうちに、操作の理由が理解できていたのだ。行動の背後にある理屈をAIが説明してくれたことで、思考の型が体に染み込んでいった。学習速度が上がると同時に、判断に迷う時間が減っていった。
アウトプットが学習を加速させた
AI学習の成果を“自分の言葉”で整理することで、理解が深まった。
記事を書く行為が、学びを一段上げた。
AIから提案された構成をもとに、実体験や失敗談を追記することで「理解して書く」フェーズに変わった。教材の進みは遅くなったが、記事を通じてAIの仕組みを深く理解できるようになった。量より質へ、入力より出力へ。学びの重心が明確に動いた瞬間だった。
現実との両立と時間の限界
学習・仕事・生活の同居
AI学習が習慣化すると、生活のすべてが連動し始めた。
朝は現場に出て、夜はフクロモモンガの世話を終えた後に4〜6時間の学習。休みの日は14時間以上、PCと向き合うこともあった。疲労を感じつつも、「理解が進む喜び」が支えだった。AIが提案するタスクを一つずつこなすうちに、迷いよりも充実が勝っていった。
続けるための仕組みを作る
根性では長続きしない。
AIが作ってくれた「次にやることの見える化」が、継続の鍵だった。翌日の行動をAIに整理させ、私が決断する。この分担が、疲労を減らし学習を安定させた。継続は才能ではなく構造――この感覚が自分の中に定着した。
学びを“任せる”から“共に進める”へ
思考が戻ってくる感覚
AIに任せきりだった頃の私は、結果だけを見て安心していた。
だが今は、AIの回答を鵜呑みにせず「なぜそうなるのか」を考える癖がついた。自分が理解していない部分を質問で掘り下げ、改善案を比較する。AIが教える側から“議論する相手”に変わった。
次の行動へのヒント
AIは、手順を示すだけのツールではない。
考え方を写す鏡として使うことで、学びは加速する。
もし今、AIに任せきりだと感じているなら、一度“なぜ”を問う時間を取ってみてほしい。そこから生まれる気づきこそが、次の成長を形づくる。
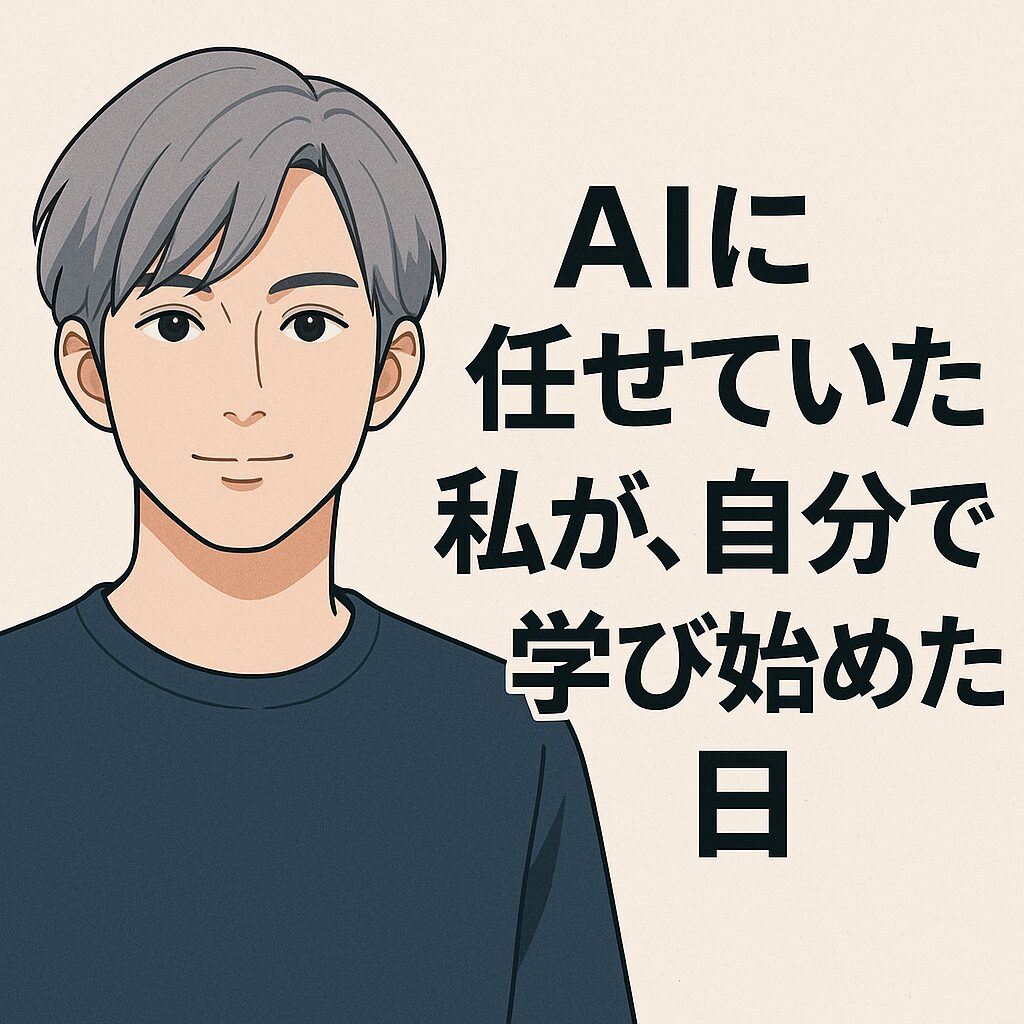
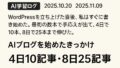

コメント