本記事では「スマパチ からくり 長スパン立ち回り」をテーマに、実戦データをもとにしたシグナル判断と非対称ロジックを解説します。
はじめに(結論)
この立ち回りをしていた当時、私はAIを勉強していません。
それでも後から見直すと、やっていたことは仮説→観察→更新→撤退の繰り返し。
結果としてAI的な意思決定になっていました。
対象はスマパチからくり。
短期のノイズが強いので、長いスパンで状態を区切り、さらに挙動の“シグナル”(※現行機のため詳細は伏せます)を重ねて押し引きします。
私が実際にやったこと(当時の運用)
1)入る前の基準を固定
- その日の**持ち回り(回転効率)**が自分の店基準を下回るなら触らない。
- イベントや日付の傾向だけで座らない。
- 店×日×機種の“癖メモ”とセットで判断。
2)座ってからは“挙動のシグナル”で短く触る
- 直近の履歴で山が続く流れは短く触る。
- **失速の兆候(間隔が伸びる/山が痩せる)**を感じたらすぐ離れる。
ここで使うシグナルはいくつかの動きの組み合わせですが、現行メイン機のため具体的な内容は伏せます。
重要なのは、
**「決めてから打つ」「崩れたらやめる」**の2点です。
3)無駄玉を削る(合法だけ)
- 保留2からの先読み停止(からくりはステージからの入賞が多いので、乗ったら止める)
- いまは1玉返しが主流 → “入賞を増やす”より外れ玉を減らす方が効く
要するに、
**入る基準(入口)・続ける基準(挙動)・やめる基準(失速)**を決めていた、というだけです。
実データのダイジェスト(抜粋)
6〜8月の収支から、代表的な部分を抜粋します。
プラス域:
+95,000(6/1)/+130,000(6/15)/+44,000(6/16)/+51,000(6/24)/+42,500(6/27)/+40,000(6/30)/+62,000(7/1)/+160,000(7/3)/+218,000(7/6)/+25,000(8/14)
マイナス域:
-11,000/-20,000/-15,500/-20,000/-9,000/-26,000/-75,000/-34,000 など
特徴は勝ちが大きく、負けが小さい“非対称”構造。
理由は単純で、シグナルが崩れたら即撤退するから。
「打つ台がなくて座った日」は負けが増える——ここでもルールが利益を守ると分かりました。
スパンの切り替え(対比)
| 種類 | 定義 | 目的 |
|---|---|---|
| 長スパン | 週/月単位。入る基準=店の傾向と配分 | 負け試合を入口で消す |
| 短スパン | 台単位。撤退基準=履歴の崩れ/アベ低下 | 負けの深追いを止める |
結論: 長スパンで“触らない日”を決め、短スパンで“粘らない”を徹底。
“オカルトじゃない”と断言できる理由
- 因果を断定しない: シグナルは“爆発の約束”ではなく、押し引きの基準。
- 反証を受け入れる: 同じ手法はエヴァには当てはまらず、私は釘(回転効率)判断だけに切り替えました。
- 更新を続ける: 効かない日・店は切る。効く条件に集中する。
これは、AIでいう
**「特徴の観察 → 閾値で意思決定 → 外れたらモデル更新」**と同じ構造。
学ぶ前から“型”だけはできていた、という話です。
今日から真似できる最小セット(AIナシでOK)
- 入る前: 最初の数千円で持ち回りを測る。基準を割ったら触らない。
- 座ってから: 挙動のシグナルが続く間だけ短く触る。
- 撤退: 間隔の伸びや失速を感じたら即降り。
- 無駄玉: 保留2から刻む/玉の挙動で止める。
- 記録: 日付・投資・回転・簡単なメモ(“山/失速”)を残す。
→ これだけで感情が入りにくくなり、再現性が上がります。
まとめ
スマパチからくりは短期ノイズが強い機種。
だからこそ長いスパン+挙動のシグナルで押し引きする。
具体的な“挙動名”は伏せますが、運用自体はシンプル。
決めて入る/崩れたら出る。
当時はAIを使っていなかったが、振り返るとAI的な意思決定の型になっていた。
その結果、勝ちは大きく、負けは小さい収支に収束しました。
🔗関連記事
関連:
🧩前回「リゼロ鬼がかりで9日連勝——短スパン仮説と撤退ルール」
🧩合法テク「止め打ちは保留2から——風車と球筋で無駄玉を削る」

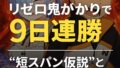

コメント